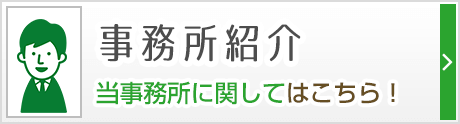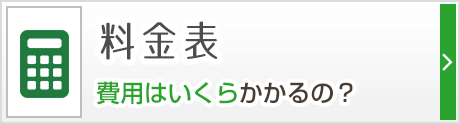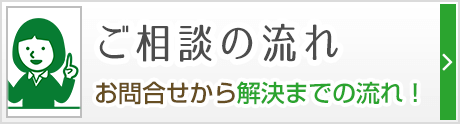コラム
- 2021.03.29
- 【生前贈与の裏技10選!】非課税枠を上手に使う!お得にする方法は!?
目次
生前贈与は贈与税の課税対象です。
しかし非課税制度を上手く活用すれば、贈与税を支払わずに財産を渡せますし、相続税の節税効果も期待できます。
今回は10種類の節税方法と、利用する際のポイントを解説します。
⑴誰でも利用できる『贈与税の基礎控除額』
贈与税には110万円の基礎控除額があり、控除額を適用する際の要件は特に無いです。
そのため年間110万円以下の贈与であれば、贈与税を支払う必要はありません。
1,000万円を1度に贈与すると、財産をもらった人は177万円の贈与税を支払うことになります。
(受贈者が20歳以上で、直系尊属から贈与を受けた場合)
しかし110万円控除は毎年使える控除ですので、100万円の贈与を10年間続ければ、1,000万円の財産を無税で贈与することも可能です。
なお贈与税は、受贈者が1年間(1月1日から12月31日)でもらった財産の合計金額に対し、基礎控除額を差し引きます。
基礎控除額以内の贈与であれば、贈与税の申告手続きは不要ですが、基礎控除額を超える贈与財産を取得した際は、申告および納税手続きが必要です。
□⑵子や孫への『住宅取得等資金の贈与』
『住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度』は、親や祖父母から住宅購入資金の贈与を受けた際に適用できる特例です。
特例を適用できるのは20歳以上の受贈者のみで、贈与財産を住宅の購入資金に充てない場合や、購入した住宅に居住しない場合は特例を受けられません。
また特例を適用するためには、必ず贈与税の申告手続きが必要です。
申告期限を過ぎると、特例は一切適用できなくなるため、申告期限内に手続きを済ませてください。
なお住宅取得等資金の贈与の非課税控除枠は、購入する住宅の契約年月日や、建物の構造によって変わります。
契約する時期が早いほど控除額が大きく、省エネ住宅を購入する際は非課税控除額が上乗せされます。
【住宅取得等資金の非課税制度の控除額】
| 住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅の場合 | 左記以外の住宅の場合 |
| 平成31年4月1日~令和2年3月31日 | 3,000万円 | 2,500万円 |
| 令和2年4月1日~令和3年3月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
| 令和3年4月1日~令和3年12月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
⑶孫やひ孫に対して適用できる『教育資金の贈与』
『教育資金教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度』は、孫やひ孫など直系卑属が、教育資金として使用するための金銭等の贈与を受けた際、最大1,500万円までの贈与が非課税になる特例です。
適用できるのは30歳未満の直系卑属で、受贈者の前年の所得が1,000万円を超える場合には適用できません。
また受贈者が30歳の時点で、教育資金として使用していない金額が残っている場合、その時点で贈与があったとみなされます。
(一定の要件を満たすと期間が40歳まで延長します。)
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度の申告手続きは、贈与財産を管理する金融機関を経由して税務署に提出するため、手続き窓口を間違えないように注意してください。
なお扶養家族の生活費や学費の支出に対し贈与税は課されませんので、生活を一緒にしている子の教育費を支払う場合に特例を適用する必要はありません。
⑷子や孫への『結婚・子育て資金の贈与』
『結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度』は、子や孫など直系卑属に対し、結婚・子育て資金として使用するための贈与に適用できる特例です。
贈与資金を結婚の挙式費用や不妊治療、子育ての際の医療費保育料などに充てる場合、最大1,000万円までの贈与は非課税になります。
適用を受けられるのは20歳以上50歳未満の直系卑属で、受贈者の前年の所得が1,000万円を超える場合には適用できません。
また受贈者が50歳に達した時点で、結婚・子育て資金として充てていない贈与財産が残っていた場合は、その時点で贈与があったとみなされます。
(贈与者が亡くなった時点で残っていた結婚・子育て資金は、相続税の課税対象となります。)
なお申告手続きは、教育資金の特例と同様、贈与財産を管理する金融機関を経由して税務署に提出してください。
⑸贈与財産の種類は問わない『相続時精算課税』
『相続時精算課税制度』は、20歳以上の受贈者が60歳以上の親または祖父母から受けた贈与財産に対し適用できる特例です。
特別控除額は2,500万円で、贈与財産の種類や用途に制限はありません。
2,500万円の特別控除額は、贈与者ごと(特定贈与者)に適用できるため、両親から受けた贈与財産に特例を適用する場合、最大5,000万円まで非課税控除額を使用できます。
注意点としては、相続時精算課税制度を適用した年分以後、110万円の基礎控除額は利用できなくなります。
(特定贈与者以外からの贈与に対しては、引き続き110万円控除を適用できます。)
また相続時精算課税制度は贈与者が亡くなった際、相続財産と特例を適用して受けた贈与財産の金額を合算し、相続税の計算をしなければなりません。
合計した課税対象金額が相続税の基礎控除額を超えた場合、相続税として税金を納めることになるため、保有財産が多い方はご注意ください。
<相続税の基礎控除額の計算式>
3,000万円+600万円×法定相続人の人数=相続税の基礎控除額
⑹自宅を配偶者に贈与する際に適用できる『配偶者控除』
贈与税の配偶者控除は、自宅の持分または自宅の購入資金の贈与に対し、最大2,000万円控除できる特例です。
結婚して20年以上の夫婦が特例を受けられる一方で、特例はその夫婦で1度ずつしか利用できません。
配偶者から金銭贈与を受けた場合、贈与資金を新居の購入資金として充て、翌年3月15日までに新居に住む必要があります。
また既に住んでいる自宅の持分贈与を受ける際は、贈与を受けた以後も引き続き自宅に住むことが条件です。
なお特例を適用する際は、贈与税の申告書の提出が必要となるため、忘れずに手続くしてください。
⑺自宅の売却する際は生前贈与で夫婦共有名義にした方が得
贈与税の特例ではありませんが、生前贈与と組み合わせて利用するとより節税効果を得られる特例もあります。
不動産を売却する場合、売却利益に対して譲渡所得税を支払うことになります。
しかし自宅の売却に対しては、3,000万円の特別控除の特例を受けられるため、売却利益が3,000万円以内なら譲渡所得税は非課税です。
また3,000万円の特別控除の特例は、不動産の所有者ごとに適用できるため、自宅を夫婦共有名義で所有していた場合、夫婦でそれぞれ3,000万円控除を受けられます。
将来的に自宅を売却する予定の方は、今のうちに贈与税の配偶者控除利用して自宅の持分を贈与し、自宅を売却した際に夫婦で3,000万円の特別控除を受ける節税方法もあります。
⑻預金を保険に変えるだけ『死亡保険金の非課税』
相続税には基礎控除額とは別に、死亡生命保険金に対する非課税控除枠が設けられています。
死亡保険金の非課税控除額は法定相続人の人数によって変化し、法定相続人が配偶者と子2人の場合は、1,500万円までの死亡保険金が非課税になります。
そのため預金の一部を生命保険に変え、死亡保険金として財産を受け取れば、非課税控除額分だけ相続税の課税対象金額を減らすことも可能です。
<死亡保険金の非課税控除額の計算式>
非課税限度額=500万円 × 法定相続人の人数
なお非課税控除を適用できる死亡保険金は、亡くなった人の死亡を原因として受け取る保険金のうち、亡くなった人が保険料を負担していた保険です。
相続人以外の人が受け取った死亡保険金に対しては、非課税控除は適用されませんのでご注意ください。
⑼運用益は非課税になる『ジュニアNISA』
ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)とは、0歳から19歳の人が利用できるNISAです。
通常、株式や投資信託の売却した際、売却益に対して譲渡所得税が課されます。
しかしジュニアNISAを利用して取得した株式・投資信託の売却利益について、譲渡所得は課税されません。
ジュニアNISAの年間非課税投資枠は80万円で、投資枠は5年間利用できるため、最大400万円分の株式・投資信託に対する売却利益が非課税になります。
(非課税投資枠で購入した株式・投資信託は、18歳まで払い出し制限があります。)
なおジュニアNISAの投資枠で購入した株式を親や祖父母のお金で購入した場合、購入金額は贈与の対象になります。
ただ年間の贈与金額が110万円以内に収まれば、贈与税は課税されませんので、無税で投資資金を援助することも可能です。
⑽家族信託は贈与税を支払わずに資産管理が可能
家族信託とは、本人が高齢になったり、自らの意思で財産を運用・処分するのが困難になった際、家族が本人に代わって財産を管理する方法です。
信託銀行への委託は、基本的に資産を増やす目的で行われるケースが多く、運用リスクも存在します。
一方、家族信託なら運用リスクを避けながら、資産運用する方法も選択できます。
また子に資産運用を委託し、委託した本人が運用益を受け取る(自益信託)の場合、贈与税は発生しません。
家族信託なら高額な委託手数料も発生しませんので、一般のご家庭でも利用できる制度です。
まとめ
非課税制度を利用して生前贈与する際は、110万円の基礎控除額の利用をベースに、贈与財産の種類や金額に応じて特例制度を活用してください。
生前贈与で財産を上手く渡せれば、その分だけ相続税の課税対象金額も減らせるため、相続税対策にもなります。
なお相続開始前3年以内に贈与を受けた財産については、原則相続財産に加算しなければなりません。
相続開始直前に生前贈与しても、節税効果が得られないことがあるため、計画的に贈与することをオススメします。
-
- 2022.09.13
- 成年後見人の業務について詳しく解説~後見開始から終了まで
- 2022.09.13
- 家族信託や遺言書の違いは?どちらを選ぶべきかについても解説
- 2021.10.19
- 家族信託の手続き一覧!流れやポイントを解説!
- 2021.03.29
- 円満な相続のために知っておきたい家族信託のメリットとデメリット
- 2021.03.29
- 正しい遺言書の書き方とは?無効にならないための5つのポイント
- 2021.03.29
- 少なくとも300万円!?成年後見制度に必要な費用感は?
- 2021.03.29
- 贈与と相続はどちらが得?金銭の生前贈与する際のメリット・デメリットを徹底解説!
- 2021.03.29
- 贈与と相続はどちらが得?不動産の生前贈与のメリット・デメリットを徹底解説!
- 2021.03.29
- 生前贈与の完全マニュアル!必ず知っておきたい概要と注意点
- 2021.03.29
- 完全マニュアル!生前贈与に必要な手続きの流れを分かりやすく解説!
- 2021.03.29
- 【生前贈与の裏技10選!】非課税枠を上手に使う!お得にする方法は!?
- 2021.03.29
- 遺言書の検認や執行とは?遺言書の作成から相続発生後までの流れを解説
- 2021.03.29
- 遺言書にはどんな効力があるの?遺言の効力について専門家が徹底解説
- 2021.03.29
- 遺言で実現できる事とは?遺言書でできることと、できないこと
- 2021.03.29
- 2020年7月10日より開始された遺言の保管制度とは